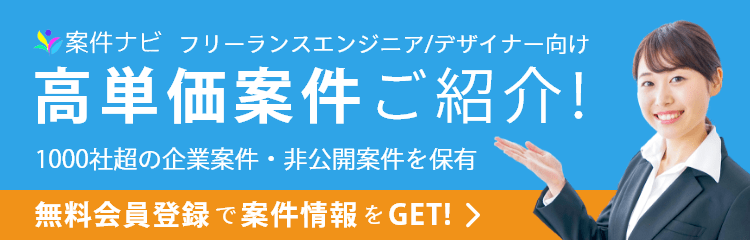フリーランスエンジニアが入るべき保険を徹底解説!

フリーランスエンジニアは自分自身で各種保険に入らなければなりません。日本は社会保険が整っているため、最低限の保険はありますが、それでは不足しているからです。会社員向けの制度が多くなっているため、フリーランスでは日本の制度を最大限活かせません。
とはいえ、具体的にどのような保険に入るべきであるか理解できていない人が多いでしょう。今回は、基本的な公的保険から意図的に加入したい民間保険まで解説します。
この記事の目次
フリーランスは標準的な保険が少ない
残念ながら日本の制度では、フリーランス向けの標準的な保険は少ないといわざるを得ません。会社員であることによって優遇される制度が数多くあるため、フリーランスのように組織に属さない働き方は、保険の面で不利をこうむりやすいのです。一部のフリーランスについては、組織に属して活動していることがありますが、ここでの組織に属するとは「雇用される」ということを指します。そのため、結局のところは「フリーランスは保険面で不利をこうむることが大半」と考えるべきです。
このような状況であることから、フリーランスは自分自身で保険を強化したり、必要なものに入ったりすることが求められます。特に、会社員以上に自分自身のことを意識する必要があるため、保険に入ることは必須だと考えても良いでしょう。
フリーランスが加入する基本的な公的保険

以下ではフリーランスの標準的な保険である公的保険について解説していきます。
国民健康保険
日本は公的保険制度が最低限は整っているため、フリーランスも国民健康保険に加入できます。国民健康保険は、いわゆる保険証を手に入れるための保険制度です。日本は「国民皆保険制度」を掲げていて、全ての人が保険証を持ち、有事の際は気軽に医療機関を受診できる制度が整えられています。
ただ、フリーランスも加入できる公的保険ですが、会社員とは異なり、保険料は全額自己負担です。会社に雇用されている場合は、会社と折半して加入する仕組みですが、フリーランスはそのような仕組みではありません。そのため、どうしても自己負担が高額になってしまう点には注意しましょう。
なお、国民健康保険は加入の義務があるため、フリーランスで売上が少ないからと加入を避けることはできません。自分を守ってくれる保険ですが、入ることによって金銭的な負担が増える点は、フリーランスになる前に理解しておきたいポイントです。
国民年金
日本の年金制度は、国民年金と厚生年金から構成されています。ただ、フリーランスエンジニアが加入できるのは国民年金のみであり、会社員や公務員と比較すると少ない状況です。支払う金額は少なくなりますが、将来的に支給される金額も少なくなってしまいます。
標準状態では大きな差が生じますが、年金を上乗せするための公的制度として「付加年金」「国民年金基金」と呼ばれるものがあります。どちらも加入は任意で、付加年金は付加保険料を納めることで年金を増やせる制度であり、国民年金基金は、追加で年金に加入するような制度であると理解すればよいでしょう。どちらも、フリーランスエンジニアとしての収入やライフプランに応じて加入するかどうかを選択します。
40歳以上のみ介護保険
フリーランスエンジニアでも、40歳以上になった際は公的介護保険への加入が必須です。日本国民に加入義務があるため、フリーランスエンジニアで収入が安定していないような状況でも加入しなければなりません。
保険料は上記の国民健康保険と同時に納める必要があり、かつ会社員とは異なって全額が自己負担です。40歳以上になるタイミングで保険の負担が変化するため、その点は抑えておきましょう。
フリーランスが万が一に備えて入るべき民間保険
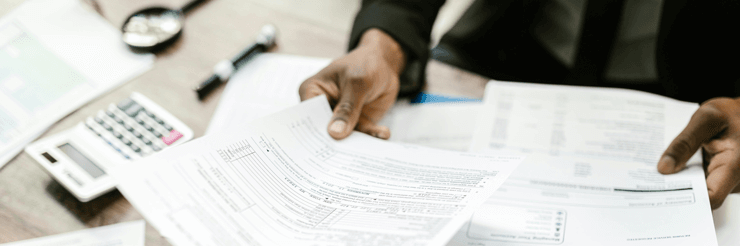
フリーランスは公的保険に加入できますが、充実しているとは言い切れません。そのため、万が一に備えて民間保険に入るべきです。
就業補償保険・所得補償保険
フリーランスが最初に意識すべき保険は、就業補償保険・所得補償保険です。これらの保険は、何かしらの理由でフリーランスとしての活動ができなくなった際に、収入面を補償してもらうために加入します。フリーランスは会社員とは異なり、案件をこなさない限りは収入を得られません。
例えば、会社員は雇用されているだけで、休暇を取っても休職しても最低限の賃金が支払われます。しかし、フリーランスは案件を受注できないと収入が完全に途絶えてしまうのです。病気などで稼働が停止してしまうと、それだけ収入に影響が出てしまい、これによる悪影響を最小限に抑えるために保険に入ります。
なお、保険の種類はいくつもありますが、収入が途絶えた際に支給されるものが大半です。そして、支給される金額や保険料は、どの程度の収入を得ているかによって決定される傾向にあります。詳細な部分は保険会社によって大きく異なるため、必ず確認してください。
賠償責任保険
業務で発生しうる賠償責任に備えて、賠償責任保険にも加入しておくべきです。会社員の場合は、会社として賠償責任を負いますが、フリーランスの場合は個人で責任を負わなければなりません。例えば、フリーランスエンジニアが納期までにアプリケーションの開発ができないと、クライアントへの賠償責任を負う可能性があります。フリーランス側に大きな非がある場合は、まとまった金額を請求されることになりかねません。
ここで重要となるのは、交通事故など不可抗力の事由であっても、賠償責任を負ってしまう可能性があることです。また、工数の見積もりに失敗したなど、フリーランス側に明らかな非がある場合も責任は避けられません。どちらの場合でも、クライアントに明らかな非がない限りはフリーランスの責任となってしまうのです。
賠償責任保険に加入していれば、万が一の場合でも保険でカバーしてもらえます。具体的にカバーしてもらえる範囲と金額は保険の内容に左右されるため、よく吟味して決定しなければなりません。適した補償の保険に加入していないと、無駄が生じてしまう可能性があります。
医療保険
入院や治療など、医療費が増加することに備えて、医療保険に加入しておくと良いでしょう。これはフリーランスだけではなく、会社員でも加入しておきたい保険です。上記で解説したとおり、日本は健康保険があるため、基本的には3割負担で医療機関を受診できます。ただ、入院費用のうち個室費用など例外的な支出が積み重なると、3割負担でも高額な出費になってしまうことがあるため、この部分をサポートするために医療保険に加入しておくのです。
また、近年は生活習慣病に罹患する人が増えていて、フリーランスが罹患すると活動に悪影響を与えます。例えば、治療を受けるために稼働時間を減らすなどがあり得るのです。治療に費用がかかり、なおかつ収入も減ってしまうというような状況に備える意味でも保険に加入することをおすすめします。
病気や怪我のタイミングは予想できるものではなく、貯蓄や収入がない状況でも突然の入院や手術などに迫られてしまうかもしれません。このような状況に陥るとフリーランスでもそれ以外でも生活に大きな影響を与えるため、安心のために医療保険には加入しましょう。
個人年金保険
個人年金保険とは、契約時に決めた年齢から一定の金額を定期的に受け取れるようにする私的年金制度です。日本では、基本的に国の制度で年金を受け取れるようになっていますが、受け取れる金額については不透明な部分があります。老後資金に不安を感じる人が多く見受けられ、これを解決する手法として私的年金が広く利用されるようになっているのです。
特に、フリーランスは組織としての退職金制度などが準備されていないため、自分自身で老後の資金を作り上げなければなりません。金融機関に預金する方法はありますが、資産運用を意識するならば、個人年金保険などを活用した方が良いでしょう。非常に多くの商品が存在するため毎月の支払額や受け取れる金額などに注目して、契約する保険を決定するようにしてください。
火災保険
可能な限り火災保険にも加入するようにしておきましょう。賃貸物件の場合は加入が必須ですが、それ以外の場合でも、加入することをおすすめします。
火災保険の基本的な目的は、火災が発生した際の金銭的な負担を最小限に抑えることです。自身が火元になってしまった場合、大きな金銭的負担を抱えることになりかねません。これを回避するために、フリーランスも火災保険に加入しておきます。
また、火災保険は、火災に巻き込まれてしまった際に家財を保護してもらうという意味合いもあります。例えば、フリーランスが業務をこなすために必須のパソコンが燃えてしまうと、10万円から20万円程度で買い換えなければなりません。このような負担を軽減するためにも火災保険は重要なのです。
なお、理想を追い求めるのであれば、地震保険にも加入しておきましょう。地震による火事は火災保険では補償されないため、より万が一に備えられます。
フリーランスが追加で加入できる公的機関の制度
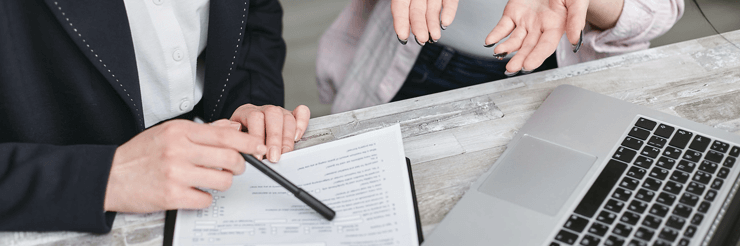
上記では、フリーランスが加入する民間保険について解説しました。ただ、フリーランスが入るべき公的機関の制度もあるため、その内容も理解しておきましょう。
小規模企業共済制度
小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供する、フリーランスや個人事業主、中小企業の経営者向けの退職金制度です。毎月、掛け金を積み立てておくことによって、退職時や廃業の際に退職金を受け取れます。
掛け金の額は月額1,000円から70,000円で選択できるため、自身の収入やライフプランに応じて選択が可能です。途中で変更することも可能であるため、最初は無理のない掛け金で加入することをおすすめします。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度は、従業員を雇用している場合に加入できる制度です。フリーランスエンジニア本人のために加入する保険ではありませんが、もし規模が大きくなり、アルバイトなどを雇用する際は加入しておくとよいでしょう。
加入する際は、事業主であるフリーランスエンジニアが掛け金を支払うなどの手続きを済ませます。ただ、従業員が退職した際は、運営機関から直接支払いがあるため、特に事務手続きなどは発生しません。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
資金繰りが悪化した際の保険として、中小企業倒産防止共済制度に加入しておくことをおすすめします。これは、掛け金を拠出しておくことによって、無担保・無保証人でまとまった金額を借り入れできる制度です。フリーランスエンジニアは怪我や病気により資金繰りが悪化することがありえるため、そのような状況に備えられます。
また、一定期間にわたって加入を続けていたならば、解約の際に掛け金の返戻を受けることが可能です。完全な掛け捨てではないため、安心して加入できることも魅力といえます。
コストが増えても保険には加入すべき
フリーランスとして働く人は「保険に入るべきであるか」と悩んでしまうかもしれません。もし、そのような悩みを持っているのであれば、保険には加入することをおすすめします。むしろ、特別な理由がない限りは保険に加入しておくべきです。
繰り返し触れている内容ではありますが、基本的にフリーランスは何かしらトラブルが発生した際に守ってもらう手段がありません。例えば、収入が途絶えた際には貯金を切り崩して生活するしかないのです。また、クライアントと契約上の認識齟齬が発生した際には、自分で問題を解決することが求められます。
このようなトラブルへの備えがないことは、非常に精神的な負担になってしまうでしょう。これが日頃のパフォーマンスに悪影響を与えることも十分に考えられます。そのため、リスクヘッジとして保険に入っておくに越したことはありません。
まとめ
フリーランスエンジニアは、公的な保険だけでは保障が不足してしまう可能性があります。日本は保険制度が充実している国ではありますが、フリーランスや個人事業主では利用できない制度もあるのです。そのため、自身で保険に加入して、万が一に備えることが求められます。
また、会社員と同レベルの保険を手に入れるだけではなく、賠償責任などの保険にも加入することが重要です。会社員ならば会社が負担するような賠償でも、フリーランスエンジニアは個人で背負わなければなりません。それらも保険でカバーできるようにすべきです。