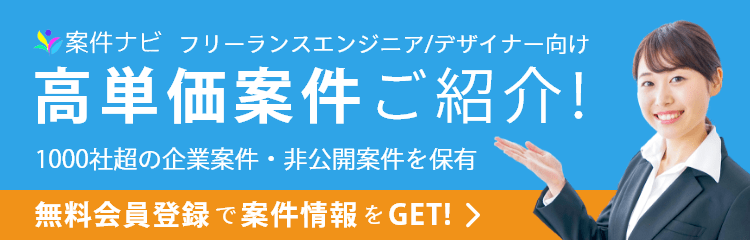構造化データとは?基本知識やSEOへの活用法を徹底解説!

構造化データとは、検索エンジンが内容を理解しやすいよう、ページのマークアップに一定のルールを持たせることを指します。単純に画面へ表示させることだけを意識するのではなく、検索エンジンでも内容を理解しやすくすることで、SEOにプラスの影響を与えるのです。
近年は重要な施策と考えられていますが、まだまだその詳細は理解されていません。今回は、構造化データの概要やSEOに与える影響などについて解説します。
構造化データとは
構造化データとは、検索エンジンに対して「このページの内容が何を意味しているか」をわかりやすく伝えるため、特定のルールに基づいてマークアップされたデータのことです。HTMLコード内にさまざまな情報を明記することで、検索エンジンがページの内容を正確に把握しやすくします。
構造化データを正しく設置することで、検索結果に「リッチリザルト」が表示される可能性を高められます。そのため、SEOの観点から構造化データを設定すべき、との理解が広がってきました。また、構造化データはGoogleが掲げる「E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)」の強化にも間接的に役立つと考えられています。
ただ、構造化データは発展途上の技術であり、複数の規格が混在するなど扱いが難しい状況です。最新情報をキャッチアップして、うまく使いこなすことが求められます。
構造化データで押さえておくべき8つのキーワード

これから構造化データを本格的に理解していくならば、最低限押さえておくべき8つのキーワードがあります。
Schema.org(スキーマドットオーグ)
Schema.orgは、Google、Microsoft、Yahoo!、Yandexといった主要な検索エンジンが共同で策定した、構造化データの使用ルールや語彙(ボキャブラリー)をまとめたサイトです。ここを参照すれば、どのようなタイプや属性名が利用できるかを確認することができます。
構造化データは、これらの検索エンジンが定義したボキャブラリーに従って記述します。そのため、不明な点があれば、まずSchema.orgを確認し、正しい記述方法や対応語彙を参照するのが基本です。
参考:Schema.org
JSON-LD(ジェイソン・エルディー)
JSON-LDは、構造化データをWebページに埋め込むための記述フォーマットの一つで、JavaScriptを使って
タグまたは内に記述します。現在、Googleが最も推奨している技術方式であり、HTMLの要素を変更せずに柔軟かつ安全に構造化データを追加できる点が大きな特徴です。基本的にはこの形式を採用するのが望ましいでしょう。
Microdata(マイクロデータ)
Microdataは、HTMLタグに直接属性を追加して構造化データを記述する方式です。itempropやitemscopeなどの属性を用います。
古いWebサイトではMicrodata形式が使われていることがありますが、現在はGoogleがJSON-LDを推奨しているため、新規実装ではJSON-LDに置き換えるケースが主流です。ここでは詳細な説明は割愛します。
リッチリザルト(Rich Results)
リッチリザルトとは、構造化データを活用することで、検索結果に強調表示された情報を表示させる仕組みです。たとえば、商品価格、レビュー評価、イベントの日程など、通常の検索結果よりも視覚的に豊かな情報が表示されます。
リッチリザルトが表示されることで、検索結果の視認性が向上し、クリック率(CTR)が高まりがちです。そのため、SEO対策としても非常に重要な要素とされています。
リッチリザルトテスト(Rich Results Test)
リッチリザルトテストは、Googleが提供する構造化データの検証ツールです。Webページに構造化データが正しく設定されているかをチェックし、リッチリザルトの対象かどうかを判定してくれます。設定ミスや不備があれば、ここで検出できるため、構造化データ導入時には必ず利用すべきツールです。
Search Console(サーチコンソール)
Google Search Consoleには、構造化データに関連するエラーや警告を自動的に検出し、通知する機能があります。リッチリザルトテストと組み合わせて利用することで、実装後の不具合の早期発見・修正が可能です。
特にサーチコンソールでは、構造化データのタイプごとに詳細なレポートが提供されています。構造化データの健全な運用において、欠かせないツールとなってきました。
Vocabulary(ボキャブラリー)
ボキャブラリーとは、構造化データで使用される用語や属性を定義した言葉の集合を指します。たとえば、「Product」「name」「price」「review」など、Schema.orgで定義されている要素です。
ボキャブラリーを誤って使用すると、検索エンジンが意図した意味で情報を理解してくれない可能性があります。意味の伝達が不完全になり、構造化データの効果が薄れてしまうのです。なお、Schema.orgではボキャブラリーの更新が頻繁に行われているため、定期的にチェックすることが重要です。
エンティティ(Entity)
エンティティとは、構造化データによって明示的に示される「対象物」のことです。具体的には、製品名、人物、組織、場所などが該当します。
近年の検索エンジンは、単なるキーワードベースではなく、このエンティティの意味や関係性を理解することが増えてきました。また、その内容を検索結果に反映させる動きを強めています。そのため、構造化データを通じてエンティティを正確に伝えることで、検索精度やSEO効果の向上が期待できるのです。
構造化データを採用するSEO面のメリット
構造化データを採用することで、SEO面にどのようなメリットがあるか解説します。
検索エンジンがWebページを認識しやすい
これまでも検索エンジンはWebサイトのコンテンツを自動的に理解してきました。しかし、検索エンジン側が独自に解釈した結果であり、実態とは乖離してしまうケースも多々見受けられたのです。
しかし、構造化データの登場により、Webサイトの運営者がコンテンツの意味を明示できるようになりました。結果、検索エンジンはコンテンツをより正確に理解できるように変化しています。
例えば、Webサイトの運営者が構造化データを正しく付与すれば、そのとおりに検索エンジンが理解してくれるのです。従来よりも適切にコンテンツを認識してもらいやすくなる点が、大きなメリットといえます。
リッチリザルトが表示される可能性がある
構造化データを導入すると、検索エンジンにリッチリザルトを表示させることが可能です。リッチリザルトとは、通常のテキストだけの検索結果に加え、より視覚的に充実した情報を表示させる仕組みを指します。
例えば、パンくずリストに対してtype属性で適切に指定します。そうすると、検索エンジンはこれをパンくずリストであると認識できるのです。また、検索結果にもわかりやすい形で表示できます。一例ですが、ページ構造を明示することで、クロール時の理解精度が向上し、検索結果にもプラスの効果を発揮します。
ただ、すべての構造化データがリッチリザルトとして表示されるわけではありません。たとえば、Googleの場合、商品の価格や在庫数、レビュー情報などがリッチリザルトとして表示される対象です。また、構造化データを設定しても、リッチリザルトが表示されないこともあるという点は理解しておく必要があります。
構造化データを採用するデメリット
構造化データの導入には多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。ここでは、導入に際して注意すべきポイントを整理します。
導入に専門知識が必要
構造化データを適切に導入するためには、専門的な知識が不可欠です。ただ、現時点では、構造化データを十分に理解して実装できるエンジニアは多くありません。人材の確保が課題であり、デメリットとなるでしょう。
また、専門知識が求められるだけでなく、現在はJSON-LDやMicrodataなど複数の構造化データ形式が存在します。しかも、どの形式を採用するかによって記述方法が異なる状況です。それぞれの特徴を理解した上で選択・実装する負担も強いられます。
さらに、構造化データは発展途上の技術で、新しい技法やボキャブラリーが次々と登場しています。 それらを逐一習得し、知識をアップデートする手間も、導入のデメリットなのです。
実装に時間がかかりやすい
構造化データの実装には通常のWebサイト制作よりも時間がかかる傾向があります。サイトの作成に加え、追加でマークアップを施す工数が増加するからです。
近年では、実装を支援するツールや、構造化データの正当性をチェックする検証ツールも登場しています。そのため、登場当初と比べると負担が軽減されました。しかし、それでも専門的な理解を要する場面が多く、実装ミスが起こりやすいのが現状です。ミスを修正するために、さらに手間と時間がかかるケースも見受けられます。
とはいえ、構造化データが普及するにつれて、実装ツールの充実やノウハウの蓄積が進むでしょう。現時点ではデメリットが目立つものの、将来的にはこうした課題は解決されるはずです。
構造化データのSEOでの活用法

構造化データを活用するためには「専門的な知識が必要だ」と感じる初心者が多いでしょう。難易度が高いと敬遠されがちです。続いては、SEOで活用するため、導入に向けた具体的な手順を細かく解説します。
導入する構造化データのタイプを見極める
最初に、導入対象となるウェブサイトに適した構造化データのタイプを見つけることがポイントです。構造化データは、多くのタイプが「Schema.org」などで紹介されているため、参考にしながら自サイトに最適なタイプを見極めましょう。
例えば、ECサイトであれば、商品情報(Product)に対応する構造化データを使うことが一般的です。商品名や価格、在庫状況といった情報を明示的に検索エンジンへ伝えられるようにします。一例ですが、構造化データを正しく導入するには、適切なタイプを選ぶことが非常に重要です。
構造化データを作成する
作成すべき構造化データのタイプを見極めたならば、実際に作成していきましょう。専門的な知識が必要で、難易度の高い部分であるため、時間をかけてでも丁寧に進めることが重要です。不安な部分があれば、構造化データの作成を支援するツールを活用しましょう。
ツールを用いる場合でも、ある程度専門的な知識が必要です。とはいえ、ツールを利用せずに作成する場合と比較すると、負担を大きく軽減できます。
Webサイトへ構造化データを反映する
構造化データに誤りがないことを確認できたら、いよいよWebサイトへ反映します。ただし、いきなり本番環境のWebサイトに構造化データを記述するのではなく、段階を踏んで作成・検証・反映することを心がけましょう。
JSON-LDを使用する場合、構造化データはWebページ内の
タグまたはタグの中に記述します。どちらに記載しても、構造化データとしての効果に大きな違いはありません。ただし、ページの読み込み速度や構造の整理といった観点から、一般的にはタグ内に記述することが推奨されています。Webサイトが動作するかテストする
Webサイトに構造化データを反映したあとは、必ずページ全体の動作確認を実施しましょう。構造化データのJSON-LDはJavaScriptを用いた記述形式であるため、反映によって予期せぬトラブルが発生する可能性もあります。
仮にWebサイトに不具合が発生した場合は、すぐに構造化データの切り戻しが必要です。原因を特定・修正したうえで再度反映をするようにしましょう。
まとめ
Webサイトでの活用が広がっている構造化データについて解説しました。Googleなどの検索エンジンにWebサイトの内容を適切に伝えるもので、設定しておくことによって、SEO対策となるなどの効果が期待できます。ただ、とにかく設定しておけば良いというものではなく、設定には一定のルールがあります。これに沿って実施しなければペナルティを受ける可能性があるため、その点は注意しておきましょう。