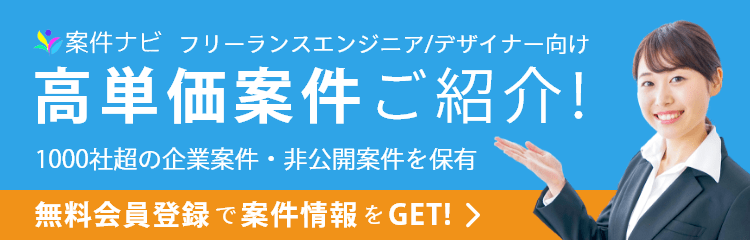Terraformとは?インフラをコードで管理するIaCの基礎と実践
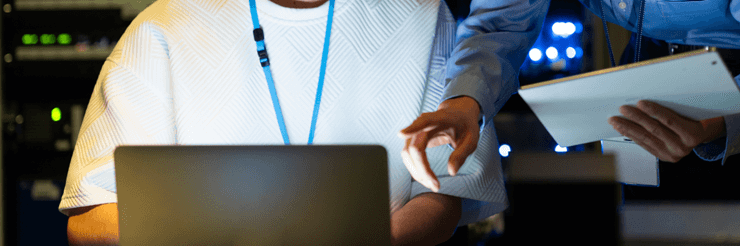
近年は、インフラを高度に管理する「IaC(Infrastructure as Code)」と呼ばれる技術が広がっています。これまではその都度、人間が手動で設定していましたが、コード化することによって業務を効率化したり、再利用性を高めたりする考え方が浸透してきているのです。
このような考えに沿って生まれたツールに「Terraform」が存在します。インフラを扱わないエンジニアにはなじみの薄いツールかもしれませんが、非常に魅力的な技術です。今回は、Terraformとはどういったものであるか、IaCの基礎を含めて解説します。
Terraformとは
最初に、Terraformとはどのようなツールであるかについて解説します。
Terraformの概要
Terraformは、インフラをコードとして管理する「Infrastructure as Code(IaC)」ツールのひとつです。HashiCorp社によって開発されており、クラウドやオンプレミスなど、さまざまなインフラ環境をコードベースで一元的に管理できます。Terraformを導入することで、複雑なインフラ構成を再現性の高い形で管理できるようになり、開発環境から本番環境まで一貫した管理ができるのです。
また、Terraformが注目されている理由として「マルチクラウドへの対応力」も挙げられます。Azure、AWS、Google Cloudなどの主要なクラウドサービスはもちろん、VMwareやOracle Cloudなどにも対応が可能です。異なるベンダーをまたいだインフラ管理の一元化が可能であることから、Terraformは特に注目を集めています。
他のIaCツールとの違い
IaCツールには、Terraform以外にもAnsibleやChef、Pulumiなどが存在しています。ただし、これらのツールとはいくつもの違いがあるため、それぞれの特徴を理解することが重要です。
まず、Terraformは「宣言的な構文」を採用している点が大きな特徴です。Ansibleなどは手続き型で記述するのに対し、Terraformでは「最終的にどうあるべきか」というゴールを定義するだけで済みます。その目標に向かって必要な操作はTerraformが自動で判断してくれるのです。結果、他のツールのように細かい手続きそのものを記述する必要がありません。
また、Terraformはクラウドサービスのリソースをプロビジョニング(初期構築)することに特化し、インフラの初期構築に強いツールです。一方、Ansibleなどはすでに構築されたサーバーに対して使われることが多いといえます。つまり、ソフトウェアの設定やインストールなどを管理する、いわゆる構成管理ツールとして活用されがちです。
さらに、Terraformはマルチクラウドの一元管理が得意である点も大きな強みです。同じコードベースで複数のクラウド環境を操作できるツールは限られています。Pulumiのように一般的なプログラミング言語で記述できるツールも存在しますが、マルチクラウドの統合管理という観点では、Terraformが一歩抜きん出ているといえるでしょう。
Terraformの特徴

続いて、Terraformの特徴を4つに絞って解説していきます。
マルチクラウドに対応
主要なクラウドプロバイダーやオンプレミス環境など、多くの環境に対応していることが特徴です。AWS、Azure、GCPなどのパブリッククラウドはもちろん、Oracle Cloudのようなサービスにも対応しています。また、これらのインフラをひとつのコードベースで管理できることがポイントです。
さらに、Terraformがマルチクラウドに対応していることで、特定のクラウドベンダーに依存する「ベンダーロックイン」を回避しやすくなります。近年、クラウド依存のリスクが懸念されるようになりました。しかし、Terraformを使えば、少ない運用負荷で複数のクラウドベンダーを使い分けできます。
宣言的な構成
宣言的な構成を採用している点も重要な特徴です。これは、ユーザーが「最終的にどうなってほしいか」という状態をコードで記述する手法を指します。Ansibleのような手続き型ツールとは異なり、ステップごとの手順を自分で記述する必要がありません。
Terraformは記述されたコードと実際のインフラ環境を比較し、差分を自動で検出・適用する機能を持っています。通常であれば、変更すべき箇所を洗い出し、作業ミスがないか確認しなければなりません。しかし、Terraformであればその工程を省略できるのです。これにより、作業の簡略化、ミスの削減、運用の一貫性や再現性の向上などが期待できます。
状態管理(State Management)
「状態ファイル」を作成し、現在のインフラの構成情報をファイルとして記録できます。これは変更の必要性の判断、インフラ変更の履歴管理、チームでの共有など運用に役立つものです。
また、状態管理がファイル化できることで、自動化ツールなどと組み合わせて利用しやすくなっています。詳細は以下で述べますが、コード化のメリットを享受しやすい仕組みと考えましょう。
再利用性が高い
構成の一部を「モジュール」として切り出すことが可能で、再利用性の高さが魅力です。たとえば、AWSにおけるVPCやセキュリティグループなど、複数の環境で繰り返し利用される要素を部品化し、何度でも使える形にできます。
しかも、これらのモジュールはパラメーター化にも対応しています。そのため、パラメーターを活用し、環境ごとに異なる設定値に対応させることが可能です。たとえば、サブネットの数やCIDRブロックを引数として変更できるようにし、構成がやや異なる環境へ流用するのです。
Terraformを導入するメリット
続いては、インフラ管理にTerraformを導入するメリットについて解説します。
人的ミスの削減
大きなメリットとして、人的ミスの削減が挙げられます。インフラの構築や変更作業をコードベースで管理できるため、手動操作による設定ミスや見落としが発生しづらいのです。
従来、インフラの構築は管理画面からマニュアル操作が求められました。ただ、複雑な構成では設定漏れや不一致が起こりやすく、運用上のリスクとなっていたのです。
しかし、Terraformでは、設定内容はすべてテキスト形式のコードファイルに記述されます。そのため、事前にコードレビューして品質を確保しておけば、人的ミスが発生しません。また、ファイルに履歴を残しておくことで、「誰が」「いつ」「どのような変更を行ったか」が明確になり、トレーサビリティの確保や運用の透明性向上にもつながります。
再利用性の向上
同じ構成を何度も使い回せる「モジュール化」の機能を備えていることもメリットです。これにより再利用性を向上でき、インフラ構築作業の効率化を高められます。
再利用性が高ければ、毎回同じ設定を一から書く手間が省け、開発スピードと運用の効率が飛躍的に向上するでしょう。共通化と柔軟性を両立できる仕組みであり、大規模なインフラ運用やチーム開発で特に効果を発揮します。
CI/CDパイプラインとの統合
TerraformはCI/CDツールとの統合がしやすい点も大きな魅力です。たとえば、GitHub ActionsやGitLab CI、Jenkinsなどと連携することで、自動デプロイや構成の自動適用が可能になります。特定のブランチへのプッシュをトリガーとして、Terraformによるインフラ構成の変更を自動で反映させるといったワークフローも実装が可能です。
また、CIパイプライン内で「terraform plan」を実行し、差分をレビューしてから、「terraform apply」で本番環境へ反映するといったプロセスも整備できます。このように、Terraformは自動化によるスピードアップと人によるレビューによる安全性の両立が可能です。Terraformを導入すれば、効率的かつ安定したインフラ運用が実現できます。
Terraformの基本的な実践方法
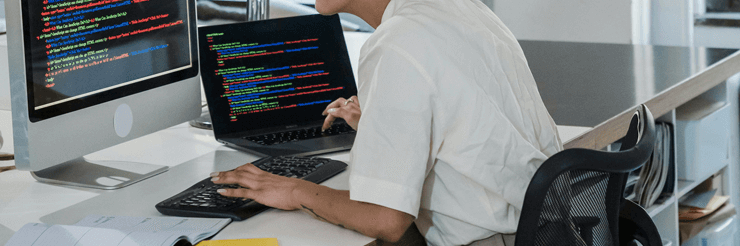
Terraformを利用するためには、いくつかの手順があります。以下では、基本的な実践方法を解説します。
terraform init
terraform initは、Terraformの作業ディレクトリを初期化するためのコマンドです。初めてプロジェクトを作成した際やAWS、Azureなどのプロバイダー設定を追加・変更した際に実行します。
このコマンドによって、Terraformは設定ファイル(.tfファイル)を解析してくれます。そして、必要なプロバイダープラグインをダウンロードし、リモート状態を管理するための設定を済ませてくれるのです。これを実行しなければ、後続のplanやapplyコマンドは利用できません。
terraform plan
terraform planは、現在のインフラと構成ファイルに記述された望ましい状態との差分を計算するコマンドです。また、Terraformが実行する予定の変更をシミュレーション表示してくれます。
この段階では実際の変更は実施されず「何がどのように変わるのか」を事前に確認するだけです。作成・変更・削除されるリソースを詳細に表示してもらい、意図しない変更を防ぐことを目的としています。Applyの前に必ず実行して確認するのが一般的な運用スタイルです。
terraform apply
terraform applyは、planで確認した構成変更を、実際にインフラへ反映させるコマンドです。ユーザーが確認・承認した後に、Terraformが必要なAPI操作を実行してクラウド上のリソースを作成・変更・削除します。Applyを実行すると、変更内容に関する最終確認が求められ、その後にインフラが構築されるという流れです。
また、適用後には状態ファイル(terraform.tfstate)も更新されます。これは、今後の操作で差分管理の基礎となるデータです。
terraform destroy
terraform destroyは、構成ファイルで定義されたすべてのリソースを削除するためのコマンドです。不要になった開発環境や、構成を一新する前のクリーンアップ用途として使用されます。Applyとは逆の操作で、削除対象のリソースが一覧表示されたうえ、承認を経て削除される仕組みです。
一括削除できる点は便利ですが、計画的に運用しないと、本番環境のリソースまで誤って削除するリスクがあります。とはいえ、CI環境では、自動テスト終了後にリソースを破棄する目的で使われることも多く、適切に活用できるとコスト削減にも貢献してくれます。
まとめ
インフラをソースコードで管理できるTerraformについて解説しました。現在は、インフラの管理方法が見直され、従来のように手作業での構築は避けるべきとされています。そのような状況下で、Terraformは非常に魅力的なツールです。
特に、Terraformは宣言的な構成であるため、従来のツールのように手順を意識する必要がありません。この点は、インフラを構築・運用するにあたって、作業効率を大きく高めてくれます。まだまだ、浸透しているツールではありませんが、この機会に導入を検討してみてください。