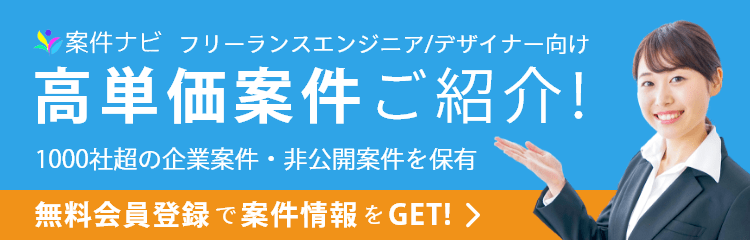インフラ構築とは?基本知識や構築手順を分かりやすく解説!

システムを運用するにあたって、非常に重要な要素がインフラです。たとえアプリケーションが開発されたとしても、インフラが存在しなければ、それを動かすことはできません。
そのため、アプリケーションを構築する前段階として「インフラ構築」と呼ばれる作業が必要になります。ITインフラを整備し、必要な機器の手配や各種設定作業を担う作業です。今回はインフラ構築の基本知識や具体的な構築手順について、わかりやすく解説していきます。
そもそもITインフラとは

そもそも「ITインフラ」とは何か、明確に理解できていない方もいるかもしれません。そこで、今回はITインフラを「ハードウェア」と「ソフトウェア」に分けて、それぞれの役割や特徴について丁寧に説明していきます。
ハードウェア
ITインフラの物理的な土台を構成するのがハードウェアです。パソコンやサーバー、ストレージなどが含まれ、データの入力から処理、保存までを担います。
パソコン
パソコンは、従業員が日々の業務をこなすために欠かせないツールです。文章作成、表計算、メール送受信、Web閲覧など、さまざまな作業を支えるITインフラの一部といえます。
現在では、多くのパソコンがネットワークに接続されており、各種サーバーやクラウドサービスと連携できるようになりました。これにより、情報共有の効率化や業務システムの利用が可能となり、業務全体の生産性向上にも貢献しています。
ストレージ
ストレージは、データを保存・保持する装置です。パソコンに内蔵されているHDDやSSDはもちろん、NAS(ネットワーク接続ストレージ)やSAN(ストレージエリアネットワーク)など、ネットワーク経由で利用するストレージも含まれます。
ITインフラにおいてストレージは、業務データのバックアップやアーカイブの保存先としての役割を持ち、その容量、アクセス速度、耐障害性が重要な評価軸になります。また近年では、クラウドストレージの活用が進んでおり、オンプレミスとクラウドを組み合わせたハイブリッド運用も必要です。
サーバー
サーバーは、ネットワーク内で複数の端末にサービスを提供するコンピュータです。パソコンもコンピュータの一種ですが、サーバーはより大規模で高性能なものとイメージするとよいでしょう。ITインフラの代表格ともいえる存在です。
サーバーにはさまざまな種類があり、ファイル共有サーバー、アプリケーションサーバー、データベースサーバー、メールサーバーなどが挙げられます。多種多様な役割を担うため、状況に応じて必要なサーバーを適切に選択しなければなりません。
また、物理的なサーバーだけでなく、現在では仮想サーバーやクラウドサーバーも積極的に利用されるようになりました。それぞれに柔軟性や拡張性といった特性が異なるため、目的や運用環境に応じて最適なITインフラを導入しなければなりません。
ソフトウェア
ソフトウェアは、ハードウェアの上で動作し、業務を遂行するためのプログラムです。オペレーティングシステムをはじめ、業務用のアプリケーションや、それらを動作させるためのミドルウェアなどが該当します。
OS
OS(オペレーティングシステム)は、コンピュータの基本動作をつかさどるソフトウェアです。多くの企業ではWindowsが利用されており、そのほかにもmacOSやLinuxなどが代表的な例として挙げられます。OSは、ユーザーがアプリケーションを動作させるための土台となるもので、ハードウェアの操作を仲介する役割を担うものです。
また、オペレーティングシステムは、ネットワーク設定、セキュリティ制御、ファイル管理といった基本機能も担当しています。重要性が見落とされがちですが、システム全体の安定性や運用性を大きく左右する、極めて重要なITインフラのひとつです。
ミドルウェア
ミドルウェアは、OSとアプリケーションの間に位置するソフトウェアです。一般的に、システム全体の連携や機能の拡張を支援する目的で導入されます。たとえば、Webサーバーやデータベース管理システムなどがミドルウェアに該当する製品です。アプリケーションを効率的に構築・動作させるための環境を整える役割を担っています。
業務アプリケーション
業務アプリケーションは、販売管理、会計、人事など、特定の業務を支援するためのソフトウェアです。自社のサーバーに導入するオンプレミス型や、クラウドサービスを利用するSaaS型などがあり、導入形態によって運用負荷は大きく異なります。
自社でアプリケーションを開発し導入する場合には、インフラ構築においてさまざまな考慮が必要です。一方で、クラウドサービスとして提供される場合には、インフラ構築で考慮すべき点はほとんどありません。
インフラ構築の基本知識
ここまで、ITにおけるインフラの基本知識について解説してきました。これを踏まえ、次にインフラ構築に関する基本的な知識についても解説していきます。
インフラ構築の概要
インフラ構築とは、ITサービスや業務システムを支える物理的、あるいは論理的な基盤を整備する作業です。一般的には、サーバーやネットワーク機器、ストレージなどを選定し、これらを接続・設定する作業を指します。また、近年ではクラウド環境の利用が増えており、クラウドとの連携もインフラ構築の一環として重要になっています。
たとえば、社内システムを導入する場合を考えてみましょう。このとき、システムを動作させるためにサーバを設置したり、クラウド上に仮想マシンを立ち上げたりする作業がインフラ構築に該当します。さらに、必要なソフトウェアをインストールして動作環境を整えることも、インフラ構築に含まれると考えてよいでしょう。
また、業務要件によっては、冗長構成の設計やバックアップ体制の整備も求められます。インフラ構築はシステム全体の品質や安定性を大きく左右する、IT戦略的な活動であるといえるのです。
インフラ設計や運用との違い
インフラ構築は、インフラ設計やインフラ運用と密接に関わっています。ただし、それぞれには明確な違いがあるため、正しく理解することが重要です。
まず、インフラ設計とは、どのようなインフラを構築するかを細かく定義するプロセスです。たとえば、業務要件や予算、セキュリティの観点から必要事項を洗い出し、それに基づいてインフラの構成や仕様を計画します。これに対し、インフラ構築は、その設計に基づいて実際に機器の選定や接続、ソフトウェアの導入などを進める工程です。密接な関係がありますが、担当する範囲が異なる点を理解しておきましょう。
また、インフラ運用とは、インフラ構築が完了した後の継続的な管理・運用を指します。たとえば、インフラの稼働状況を監視したり、障害発生時に対応したりといった作業です。設計・構築・運用は一連の流れとして密接に連携していますが、それぞれが異なる専門性を必要とするため、適切な役割分担が欠かせません。
インフラ構築の具体的な作業手順

インフラ構築を成功させるためには、作業を分解し、段階的に進めることが重要です。以下では、インフラ構築に必要な作業をより具体的に整理し、それぞれの手順で何を実施するかについて解説していきます。
要件定義
最初に要件定義を実施し、インフラがどのような目的で構築されるのかを明らかにします。具体的には、導入するアプリケーションの目的や利用者のニーズ、運用体制、予算、セキュリティ要件などの明確化です。要件定義が曖昧なままだと、後の工程で認識の齟齬が生じる原因となってしまいます。
また、要件定義においては、認識の齟齬を防ぐために、要件定義書の作成が不可欠です。関係者同士の議論で導き出された結論を文章として残しておきます。これにより、後に認識の違いが発生した場合でも、誰が誤っていたのかを明確にできるのです。また、文書化しておくことで関係者が内容を容易に参照でき、業務の効率化にもつながります。
設計
要件定義が完了すれば、次に設計フェーズに進みます。この段階では、要件を満たすために以下の内容を決定していきます。
- 必要なハードウェア
- ソフトウェア
- ネットワーク構成
- セキュリティ対策
- バックアップ体制 など
これらを整理し、具体的な構成案として図面や仕様書に落とし込んでいきます。また、設計には「基本設計」と「詳細設計」があり、それぞれを順に実施すべきです。
まず基本設計では、全体構成やシステム方式を確定させます。その後、詳細設計で具体的な設定項目やパラメータを定義しなければなりません。いずれの工程においても、設計の精度が高ければ高いほど、後続の構築やテストがスムーズに進みます。そのため、多少時間がかかったとしても、丁寧かつ慎重に設計作業を進めることが重要です。
構築
設計が完了すると、実際にインフラを構築する作業に入ります。物理サーバーやネットワーク機器の設置、あるいは仮想マシンやクラウド環境の設定からスタートし、OSやミドルウェアのインストール、各種セキュリティ設定までの実施が必要です。
構築作業では、設計書に忠実に従うことが求められます。言い換えれば、構築時に迷いが生じないよう、設計段階で十分に詳細を詰めた設計書を作成しなければなりません。各機器の設定ミスを防ぐためにも、設計書だけでなく、正確な手順書も準備し、構築担当者がその内容に従って確実に作業できるようにしましょう。
また、構築後には設定内容のエビデンスを取得し、それをドキュメントとして残すことがポイントです。どのように設定をしたかを記録しなければなりません。記録することで、運用中にトラブルが発生した際も迅速に確認・対応できます。
テスト
インフラ構築においても、構築完了後にはテストを実施しなければなりません。設計通りにインフラが正しく機能しているかどうかを検証します。たとえば、サーバーやネットワーク機器が正常に通信できているか、バックアップが正しく取得できているかなどです。
テストでは、単体テスト、結合テスト、性能テストなどの実施が一般的です。ただ、どのテストが必要かは、構築するインフラの内容によって異なります。目的のないテストは、工数やコストの無駄につながりかねません。要件定義や設計の段階で、どのテストを実施すべきか明確にしておくことが重要です。
運用
テストまで完了すれば、いよいよインフラが実際に運用される段階に入ります。これはインフラ構築の作業そのものからは一歩離れた工程ですが、構築時点で運用を意識しておくことが非常に重要です。
たとえば、構築段階で運用手順書を作成しておき、トラブル発生時の対処方法や運用ルールを明確にしておきます。インフラを安定的に運用していくためにも、運用を見据えた構築作業を心がけることが大切です。
インフラ構築で意識すべきポイント
インフラ構築は、単なるシステム導入作業ではありません。業務の継続性や効率性を大きく左右する、非常に重要な取り組みです。そのため、構築時には以下のポイントを意識し、より安定したインフラ環境の構築を目指してください。
目的や範囲の明確化
インフラ構築を成功させるためには、目的や範囲を明確にすることが不可欠です。何のためにインフラを構築するのか、どこまでを対象とするのかをはっきりさせましょう。たとえば、新しい業務アプリケーションの稼働や既存システムの更新といった目的により、求められる要件や構成は大きく異なります。
また、構築対象に社内ネットワークやクラウドサービスが含まれるかどうかなど、適用範囲の明確化も必要です。範囲が曖昧なままでは関係者を特定できず、結果としてスケジュールの遅延や要件の食い違いなど、さまざまなトラブルに繋がります。
運用方法の検討
インフラは構築して終わりではなく、その後継続的に使用されるため、運用方法についても事前に検討しておく必要があります。たとえば、ログの監視体制を整え、異常があった際に迅速に対応できるよう、対応者や連絡先・具体的な手順を定めておくことが重要です。また、バックアップの取得頻度や保管期間など、長期的な運用方針も構築段階から検討しておくとよいでしょう。
場合によっては、インフラ運用を外部ベンダーに委託することもあります。その際には、委託先との役割分担や報告ルールを明確にし、責任の所在が曖昧にならないように注意が必要です。
まとめ
アプリケーションなどの動作に不可欠なITインフラの構築には、多くの要素と検討事項が存在します。ITインフラにはハードウェアとソフトウェアの両方が含まれ、複数の構成要素を意識しなければなりません。これらを理解し、適切にインフラ構築するためには、基礎知識をしっかりと身につけておくことが重要です。
また、アプリケーション開発と同様に、インフラ構築にも「要件定義」「設計」「構築」「テスト」「運用」といったフェーズがあります。段階ごとに丁寧に取り組むことで、安定的かつ信頼性の高いITインフラを構築することができるのです。