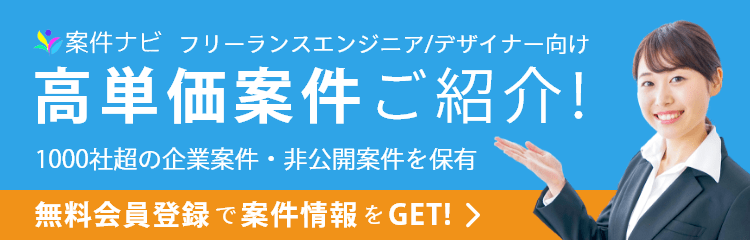クライアント証明書とは?必要性や仕組み、SSLサーバー証明書との違いを解説!

セキュリティを高めるための技術として、クライアント証明書と呼ばれるものがあります。広く利用されている技術のため、耳にしたことがある方も多いでしょう。実際に、端末にクライアント証明書が導入されているケースも珍しくありません。
一方で、利用が広まってはいるものの、具体的にクライアント証明書がどのような役割を持つのか理解できていない人もいるはずです。社内や管理者からの指示に従って導入しているだけという場合も多いでしょう。そこで今回は、クライアント証明書とはどのような技術なのか、概要から必要性や仕組み、さらにSSLサーバー証明書との違いなどを解説していきます。
クライアント証明書とは
クライアント証明書とは、接続元であるクライアントの身元を証明するために導入される電子証明書です。主に個人の端末に導入され、アクセス元の利用者が誰であるかを証明するために利用します。サーバー側は、クライアントに導入されているクライアント証明書を参照し、アクセスが許可されるかどうかを確認する仕組みです。
クライアント証明書の中には、PKI技術を利用して発行される公開鍵と秘密鍵のペアが含まれています。セキュリティ技術の詳細は割愛しますが、これらの鍵を利用して正当な利用者であることを証明できるのです。サーバーは鍵の内容を参照することでクライアントの正当性を評価し、不正アクセスを防ぎます。
加えて、クライアント証明書を導入することで、通信を自動的に暗号化できます。本来はSSL証明書などを利用して暗号化を実施する必要がありますが、クライアント証明書を利用していれば別途の手間がかからない仕組みなのです。
クライアント証明書とサーバー証明書の違い
クライアント証明書と間違えられやすいものに、サーバー証明書があります。どちらもPKI技術を利用して発行される電子証明書であるため、混同してしまう人も多いでしょう。しかし、これらは役割が異なるため注意しなければなりません。
サーバー証明書は、クライアント証明書とは異なり、サーバーの正当性を証明するためのものです。例えば、接続先のサーバーがフィッシング詐欺などの悪意あるサーバーではないことを証明します。事前に複数の手続きを経てサーバーの正当性を証明しておき、それをサーバー証明書として管理するのです。
実際、サーバー証明書には、偽造されないように公開鍵や暗号方式、共通鍵暗号方式で作成された情報が保存されています。これを用いてクライアント側との暗号化通信を実現し、正当なサーバーだけが内容を解読できるようになっているのです。
クライアント証明書の使用例

続いては、クライアント証明書の具体的な使用例を解説します。
二要素認証の実現
クライアント証明書の代表的な使用例として、二要素認証への導入が挙げられます。二要素認証とは、複数の認証手段を組み合わせ、どちらも認証できた場合にのみ正当なアクセス元であると評価する手法です。
例えば、一般的なサービスではIDとパスワードでログインできるようになっています。しかし、これだけでは情報が漏洩した際に不正アクセスされてしまうリスクを払拭できません。そこで、このIDとパスワードにクライアント証明書を組み合わせ、「IDとパスワードが正しい」かつ「クライアント証明書が導入されている端末」でのみアクセスを許可する仕組みとするのです。こうすることで、仮にIDやパスワードが漏えいしても、第三者が端末ごと盗まない限り不正アクセスは困難になります。
また、クライアント証明書は一度導入しておけば自動認証が可能な場合が大半です。そのため、実質的にはユーザーの利便性を損なうことなくセキュリティを高められます。そのため、広く採用されるようになってきました。
社外からのVPN接続
社外から組織内へVPNアクセスする際にも、クライアント証明書が役立ちます。端末にクライアント証明書を導入しておけば、IDやパスワードなしでVPN接続できる仕組みを実装するのです。これにより、接続の手間を軽減できます。
また、クライアント証明書を導入しておけば、接続元のデバイスが部外者のものである可能性を大幅に下げられます。IDとパスワードだけで認証している場合、それらが漏洩すると社内へVPN接続されるかもしれません。しかし、端末とクライアント証明書がセットになっていれば、盗まれた端末のロックを破らない限り不正アクセスは困難です。
Webアプリケーションの認証
Webアプリケーションの認証にもクライアント証明書が利用されることがあります。主に社内システムの認証に導入されるケースが多く、VPN接続の仕組みに近いと考えてもよいでしょう。
一般的にWebアプリケーションはIDとパスワードを用いてログインする仕組みです。ただ、社内システムでこの操作を何度も行うのは手間がかかってしまいます。そこでクライアント証明書を用いたログイン方式を導入することで、IDやパスワードの入力を省略しつつセキュリティを担保できる仕組みを構築するのです。
BYODのセキュリティ強化
従業員が私物のデバイスを活用するいわゆるBYODの際にも、クライアント証明書が役立ちます。私物のデバイスはセキュリティの担保が難しいですが、クライアント証明書を組み合わせることで状況を大きく改善できるのです。
例えば、社内システムへのアクセスを「クライアント証明書が導入されているデバイス」に限定します。事前に承認されたデバイスからのみアクセスを許可できるため、社外からの不正アクセスを制限できるのです。また、クライアント証明書を発行する前にウイルスチェックを義務付けるなど、よりセキュリティを高める方法も考えられます。
ただし、クライアント証明書を導入すれば必ず安全というわけではありません。デバイス側に問題があるとセキュリティホールとなる可能性が高まります。セキュリティを高めるために、組織としてのルール作りが欠かせません。
クライアント証明書の必要性

クライアント証明書の具体的な使用例を踏まえて、必要性を改めて解説します。
セキュリティの強化
クライアント証明書が必要となる大きな理由は、セキュリティの強化です。近年はサイバー攻撃が多様化しているため、可能な限りトラブルを防ぐ手段としてクライアント証明書が求められます。
まず、クライアント証明書を利用することで、悪意のある第三者がシステムへ侵入することを防ぎやすくなります。完全に防げるとは断言できないものの、リスクは大幅に下げられると考えましょう。デバイスが盗まれ、さらにデバイスのログインパスワードなども突破されない限りは、比較的安心です。
また、クライアント証明書を活用した通信は自動的に暗号化されます。平文で通信すると情報が盗聴される可能性がありますが、クライアント証明書を利用していれば、盗聴のリスクの回避が可能です。こうした点もセキュリティ強化に役立つといえるでしょう。
ユーザ認証の効率化
クライアント証明書を利用するとユーザー認証を効率化でき、業務改善にもつながります。可能な限り、認証作業をクライアント証明書に置き換えることで、IDやパスワードの入力を省略できるでしょう。1回あたりの時間は短くても、積み重なれば大きな業務効率化につながります。
ただし、クライアント証明書を使ってログインするためには、対応したシステムが必要です。現在利用しているシステムが対応していない場合は、改修コストがかかる可能性があります。導入の際には、こうした費用や対応状況も考慮することが重要です。
セキュリティや認証の制御
クライアント証明書は管理者側で無効化することが可能です。もしデバイスが盗まれたなどのトラブルが発生した際は、無効化することでセキュリティリスクを最小限に抑えられます。
IDやパスワードを利用していると、漏洩したであろう情報を、すべてのシステムなどで無効化しなければなりません。社内システムなど、大量のシステムが稼働している場合は大きな負担です。権限の停止漏れによるトラブルが生じてしまう可能性もあります。
しかし、クライアント証明書を軸に仕組みを構築していれば、これを停止するだけですべての認証も停止されます。管理者側で制御しやすい体制を整えるという観点でも、クライアント証明書には大きな意味があるのです。
クライアント証明書を導入する流れ

実際にクライアント証明書を導入したい場合、どのような流れになるかを解説します。
発行元の選定
最初にクライアント証明書を発行してもらうベンダーを選定しましょう。複数の企業が選択肢に上がるため、比較して決定しなければなりません。例えば、日本で有名な企業としては「GMOグローバルサイン」がクライアント証明書を発行しています。
発行元によって、クライアント証明書の維持費用や信頼性に違いが出ます。特に費用は変化しやすい部分であるため、どのようなライセンス形態なのかを含めて比較しましょう。
申し込み
発行元が決まったならば、クライアント証明書の申し込みを進めなければなりません。どのような資料が必要となるかはベンダーによって少々異なります。申込者の情報などが必要となるため、指示に沿って準備しましょう。
申し込み内容に不備があると、クライアント証明書の発行が遅れる原因となりかねません。他の作業に悪影響を与えることも考えられるため、必ず確認してから提出するようにしてください。
審査
クライアント証明書はセキュリティに関わることから、申し込み内容が審査されます。具体的な審査内容は公開されていませんが、申込者の情報が確認されていると考えてよいでしょう。例えば、申し込んだ法人が実在するかどうかなどが確認されているはずです。
審査を実施している間は、完了するまで待機しなければなりません。どの程度の期間、審査に時間がかかるかはベンダーによって異なるため、急ぐ場合は事前に確認しておきましょう。申し込み内容によっては時間がかかることもあるため、場合によっては段階的に手続きをするなど工夫が必要です。
証明書の発行
審査が完了し、問題なく通過できれば、クライアント証明書を発行できるようになります。近年はクラウドサービスでクライアント証明書を管理できるケースもあるため、基本的には自分で作業することになると考えましょう。
なお、発行したクライアント証明書は、利用者の端末へとインストールする必要があります。Windowsの場合、以下の手順でインストールします。
- 証明書ファイルをダブルクリック
- 証明書インストールウィザードが表示される
- ストアの選択
- 証明書ファイルの選択
- パスワード入力
- 証明書ストアの指定
なお、これ以外にもクライアント証明書をインストールする方法はあるため、場合によっては使い分けしてください。また、OSにクライアント証明書をインストールするだけではなく、ブラウザやアプリケーションで設定が必要な場合もあります。これも併せて確認しておきましょう。
まとめ
セキュリティの向上に役立つクライアント証明書について解説しました。接続元となるクライアント側に導入する証明書で、アクセス元の正当性の証明や通信の暗号化に利用されます。また、セキュリティだけでなく、業務効率化にも活用されるようになってきました。
非常に利便性の高い技術ですが、発行にあたっては審査などの手続きが必要です。さらに、クライアント証明書を維持するためにコストがかかる場合もあります。セキュリティを高めるうえではコストがつきものなので、その点も考慮しながら活用を検討してみてください。